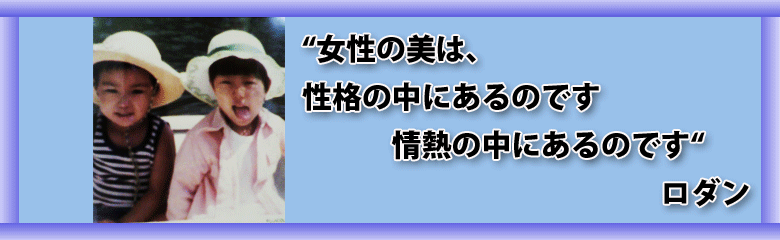自分語り > 幼年時代
団塊の世代と呼ばれる私が育ったのは、東京はまだ緑も空き地も多く残された、
杉並区方南町だった。
育った、と言えるかどうか、そこには多分、2〜3年しかいなかったと思う。
記憶にある住まいの最初が方南町なのだ。
方南町といっても当時は地下鉄が無い時代だったから、笹塚駅と代田橋駅の中間で、
駅からは近くはなかったと思う。家のすぐ傍の大きな通りを、後に“環八”と言った。
通りの坂の上には“石川五右衛門”が釜茹でにされた大きな釜を屋根に乗せたお寺があった。4月8日、そこでは甘茶が振舞われた。
長い行列に連なって、柄杓で注がれる甘茶を飲みに行った。別の方角にある、木立に囲まれた乙羽信子の屋敷を子供たちで見に行ったり、空き地で男の子たちとチャンバラをしたり、家の横を流れる小川に七夕飾りを流したり、そんな子供時代だった。
家は、道を通る人が、「“鶏小屋”と思った」というほどの古い粗末なものだった。
薄い杉板の外壁、中は新聞紙を重ねて張った壁、冬は木枯らしが家の中を吹き抜ける隙間だらけの家だ。流しだけの台所と汲み取り便所(トイレ、などという代物ではない)は外にあったから、冬は寒いというより痛い、だった。
今でも足の裏に、あの痛い冷たさを覚えている。
それでも母は、二間あったその家を我が家として愛しんでいたらしい。
広くはないが庭があり、柿、梨、無花果などの木があった。但し借家なので、
「今にお金を貯めてこの家を買い取りたい」と、口癖のように言っていた。
母は、その頃はまだ珍しい、外で働く女性だった。
朝寝坊の日曜日には、私が一番に起き出して、隣で寝ている両親の布団へ遊びに行く。
父が膝を立ててくれて、その上を私は滑り台のように滑って遊ぶのだ。
何回やっても父は怒らない、笑って長い脛を立てていてくれる。あの掛け布団の絹のような肌触りを、今も思い出す、母は布団に潜ったまま、
「布団が駄目になる、止めなさい」と言ったけれども。
日曜日は必ず、父が朝御飯の支度をした。母は遅くまで寝ていた。
私がお豆腐と揚げと納豆を買いに行く。
“お豆腐と揚げのおみおつけと納豆の朝御飯“は父の定番だった。
クリスマスイブの夜だった。真夜中、何かの気配で目が覚めた。
窓を見たが、誰も居ない。サンタクロースはまだ来ていない、と思った途端、
枕元に包みがあった。
「サンタさんが来た!」叫んで私は包みを開けた。確信していた。
思ったとおり、サンタさんはお願いしたピアノを持ってきてくれた、小さな卓上ピアノを。嬉しくて、真夜中、キンキンと指で弾いた、曲になっていなかったけれども。
父と母が隣で目覚めて、でも黙って笑って私を見ていた。
やはりクリスマスだったのだろう、そこには大きな輝くクリスマスツリーが
飾ってあった。私の憧れのクリスマスツリーが。
ダンスホールだった。大勢の大人たちが踊っていた。
父の言い付けで、私は楽団の人に曲を頼みに行った。
やがて賑やかな曲が始まった。みんなは今までどおりのゆったりした踊り方をしている。父と母は、跳んだりはねたり、曲に合った踊りをした、とても愉しそうな二人だ、何だか自慢したいような嬉しい気持ちになった。
進駐軍(当時日本は一時、米国の占領下にあった)で仕事していた父は、カタコト英語を話し、家の中では母とも英語で挨拶を交わしたりして、私にもそうした。
朝は、「グッモーニン!」と起きて、「グッバーイ!」と出掛け、
夜は、「グンナイ」と寝る。
家で大工仕事をしている父が、煙草を、と言う。母が煙草に火を点けて、私に持っていかせる。小学校上がる前の私には煙草の持ち方がわからない。
途中で火が消えると、「消えちゃったよ」と、母の元へ持っていく。すると母は、
「火が消えそうになったら、こうして吸うと火がよく点くのよ」と私に教えた。父は咥え煙草で大工仕事をした。
私は赤ん坊の頃から、母の友人が集まって麻雀をする部屋の中が真っ白になっている煙草の煙の中で育った。
父がもの凄い雷雨の夜、素っ裸になって庭に出て、「気持ちがいいぞー」と、
身体中を石鹸だらけにして洗っていた、母が笑ってそれを見ていた。
これが、父がこの家にいた私の記憶だ。
父は永い“出張”なのだった。
私は毎朝、勤めに行く母に連れられて保育園に通っていた。
“隣保舘”と言えなくて、「ピンコンカン」と言っていたと、後に母から聞かされた。
この頃覚えたのが、パティー・ペイジが唄った“テネシー・ワルツ”だ。
毎朝、毎朝、母はこの歌を唄いながら、私に教えながら歩いたのではないかと思う。
I was dancing with my darling to the tennessee waltz….
“ある時、私が私のダーリン(恋人)とダンスを踊っていたら、そこにお友だちが来たの、私は恋人を友だちに紹介した。二人はダンスをしたの。そしたら、その友だちは、私のスイートハート(恋人)を私から盗ってしまった。あの夜のことを私は思い出している、あのテネシー・ワルツを、、”
と、歌の意味まで教えてくれた、幼い私に。
その頃母には、恋人がいた。私のこともとても可愛がってくれた、母よりもかなり年下の人だった。私を抱いて、ホッペをなめずり回す可愛がり方だったが、私はあまり馴染めなかった。
九州から母方の従兄が上京した。九大を卒業したばかりで、我が家からしばらく仕事の研修に通った。ひとりっ子の私は、降って沸いたお兄ちゃんにすっかりなついてしまった。優しくて遊んでくれる、頼もしいお兄ちゃんだった。
お兄ちゃんが九州へ帰る日が来た。
「帰っちゃいやだ、ここのお兄ちゃんになって」と、駄々をこねることの無いと言われていた私が、猛烈に駄々をこねた。
けれどもお兄ちゃんを引き止めることはできなかった。
母と上野駅まで送って行くことになった。
当時は、新幹線は無論のこと、まだ特急列車もなく、蒸気機関車だった。
上野から九州まで普通列車で20数時間、お兄ちゃんの鹿児島までは2日がかりだった。
上野駅のプラットホームで、機関車の乗車口に立って、お兄ちゃんが私を見下ろしていた。私はお兄ちゃんが本当に行ってしまうのが淋しくてならなかった。
多分、泣きべそをかいていたのだろう。お兄ちゃんが冗談半分に言った。
「マッコ、じゃあ、お兄ちゃんと九州へ行くか?」
「うん、行く!」言うが早いか私はお兄ちゃんの立っている機関車の方へ飛び乗った。
「え!マコちゃん、ほんとに行くの?」母があわてて訊いた。
「行く、行くもん」
鹿児島のお兄ちゃんの家は、国鉄の官舎で、鉄筋コンクリートの大きな建物だった。
家の中はとても綺麗で、片付いていて、テーブルで食事をする食堂があった。
お兄ちゃんのおじちゃん(お父さん)とおばちゃん(お母さん)と、それに、大きなお姉ちゃんとちいちゃい兄ちゃん(弟)が居た。こんなに大勢で暮らしたことなどなかった私は、ビックリした。
「ヨシオ、あんた、なんでこんなこまい子、連れてきちょったと?」
「マッコちゃんが行くちゅうたもん」
「いくら、こん子が行くちゅうたかて、こーんなこまい子、どうするね」
おばちゃんがお兄ちゃんに言っているけれど、私はもう好奇心でいっぱいで、広い家の中をあちこち見ていた。口髭を生やした、ちょっと怖そうなおじちゃんは何にも言わない。お姉ちゃんが私をかばうように傍に来てくれた。ちいちゃい兄ちゃんが私をじっと見ていた。
真っ青な海が目の前に広がった鹿児島の暮らしは、とても素敵だった。おばちゃんはいつも家にいて、家の中を綺麗にしたり、お料理やおやつをつくってくれて、本物のお母さんだった。おやつを家で作るなんて!
お姉ちゃんは、ほんとのお姉ちゃんのように私の面倒を見てくれ、着替えひとつ持たずに来た私がなんの不自由もしなかった。
おばちゃんは私を幼稚園へ連れて行った。
東京から来た女の子、と、私はみんなから大事にされた。幼稚園は保育園とずいぶん違うところだった。お金持ちの子ばかり集まっているみたいな気がした。
先生は私にオルガンを弾かせた。
私は「結んで開いて」しか弾けなかったのだけれども。
私のオルガンに合わせてみんなが歌ってくれるのは、とても気分がよかった。
東京から私の着替えの入った小包が届いた。
開けたとき、ちょっと驚いた。今の私は全部、シンピンを着ているのだった。
食べ物の好き嫌いの激しい私は、色とりどりでいっぱい材料を使ったおばちゃんのお料理が、綺麗だけれども食べられない。
東京では、卵と骨の無いお魚の煮付けとジャガイモの煮物とホウレン草のおひたししか食べなかったのだ。お野菜はまったくダメだった。
おばちゃんは、どんな野菜もすべて脇に寄せてしまう私を見て、野菜を箸で取れないくらい細かく切って、全部が混ざって分からなくなるほど火を通したチャーハンを作った。
「おいしい!美味しいね」恐る恐る食べた私が、ビックリするほど美味しくてこう言ったのを、おばちゃんは目を細めて喜んだ。
お姉ちゃんはどこへ行くにも私を連れて行ってくれた。お兄ちゃんたちもみんな可愛がってくれた。私は、この家が自分の家族だと思い始めていた。
東京の母から手紙が来たけれど、私は、
「とうきょうのおじちゃん、おばちゃんへ」と書いて、
「わたしはかごしまのおとうちゃんとおかあちゃんの子になります」と、返事を出した。
お正月には、着物を着せてもらって、写真屋さんでお姉ちゃんとおばちゃんと一緒に、
写真を写してもらった。
私は毎日お友だちと、海の近くのクローバー畑で遊んだ。
それは寝転がると気持ちのいいクローバーの絨毯だった。
ある日、遊びから帰ると玄関に、大人の男物の靴と女物の靴があった。
ドキリとした私は、そっと部屋を覗いた。東京の父と母がそこにいた。
私を見つけた母が手を差し出した。私はさっと、おばちゃんのところへ駆け寄った。おばちゃんの陰に隠れて母を見た。よその人たちのような気がした。父と母は、私が学校へあがるのだから、と迎えに来たのだ。
「いや、東京へは行かない、ここがマッコのおうちなの、ここのおとうちゃんがあたしのおとうちゃんで、おかあちゃんがおかあちゃんなの」と、必死で言った。
この家にずっと居たかった。
杉並区方南小学校へ、私は入学した。
父は、また“出張”に出た。
私が小学校へあがると、母は、年配の女性を私の養育係兼お手伝いさんとして住み込みで雇った。日中、母が留守のためである。
“おばあちゃん”と呼んだが、今考えるとその女性は“おばあちゃん”と呼ばれるほどの歳ではなかったのかも知れない。声も動作も大きな、元気な人だった。
しかしこの女性との生活の記憶はまったく無い。
母の説明によれば、この人が、井の頭公園へ私を遊びに連れて行って、ボートに乗った、と報告した。が、昼食にビールを呑んでボートに乗ったと言う。酔ってボートを漕いだと聞いて、母はその日のうちに暇を出した、と言った。
次に来たお手伝いさんは、見るからにお婆ちゃんだった。母の仲の良い友人の母堂であるその人は、背中が曲がって背の低い、髪も少し薄いお年寄りだった。子供心に、こんな歳をとった人に、それも友だちのお母さんを使用人に雇うなんて、と居心地の悪さを感じた。
“おばあちゃん”と、私も母もそう呼んだこの人は、とても優しい気持ちの人で、私と母を誠実に守り、考えてくれた人だった。
家の中の仕事を一切、母はこのおばあちゃんに任せきっていた。
母は、仕事から帰ると、支度のできている食事をし、片付けも何もしないで、自分の時間となる。私は、食事するのもおばあちゃんと二人きりで、私を寝かせるのも、すべておばあちゃんの役目なのだ。私は、このおばあちゃんに育てられた。
おばあちゃんは、毎晩寝る前、私にお話を聞かせてくれた。それは、毎晩違う話だった。静かな、特別な声を出すわけでもないおばあちゃんの語りは、私を知らない世界へ誘った。
時々、母も一緒に聴いて、
「おばあちゃんの話は本当に面白い」と言った。
私がせがんで繰り返し話してもらった“おんちょろちょろの穴覗き”は、コソ泥に入った男が、泥棒する前に見つかってしまい、その家の独り暮らしの老人に頼まれてお経をあげることになるのだが、お経なんて知らないコソ泥君、俄仕立ての出鱈目なお経を読む。
それが、その場に出てきた鼠などを駆使した、なんとも奇妙なお経なのだ。おばあちゃんの一見そっけないような語りが、私の想像力を掻き立て、もう目の前に見えるようで可笑しくてたまらないのだ。何回聴いても可笑しくて、笑いが止まらなくなってしまう話だった。
後年知ったことだが、おばあちゃんの話は、落語や民話など日本の古典からのおばあちゃんのアレンジだったようだ。
父が、深夜久しぶりに帰ってきたとき、私は父を恐れた。
常日頃、母は父を、「稼ぐとそれ以上にお金を使ってしまう、呑んだくれ」と言っていたから。
襖を少しだけ開けて覗いた私に、
「マッコ、ほら、お土産だ」と言って放り投げた紙袋を、
「もう遅いから、あした見る」と言って私は開けなかった。
母に遠慮したのだ、父の帰りを喜んではいけないような気がして。
父と母は隣の部屋で、何か話し合ってるような、子供には無縁の静けさになった。
と、急に、激しい言い合いになって、ドスンと畳が響いたかと思うと、荒々しい気配になって父が怒鳴った。父を怒らせるようなことを母が言った、と子供心に思った。
母の悲鳴が聞こえ、
「人殺し!」という叫びが聞こえた。
「なにを!もう一遍言ってみろ」と激怒した父が言った。
「人殺し!」
「もう一遍言ってみろ」
「人殺し」
「もういっぺん」
聞こえなくなった。
布団の中で息を殺していた私の耳に、何も聞こえなくなった。
翌朝、父の姿は無かった。母の頬に痣があった。
ある日、母がスーツ姿で、私を連れて出かけた。
「何が欲しい? 何でも買ってあげる」
私は親に物をねだらない子だった。何か買って欲しいなどと言うことは無かった。
うちが貧乏なのをよく知っていた。母の言葉は、私を得体の知れない不安に陥らせた。
確固とした母の雰囲気に断れないものを感じて、私は、
「ハーモニカが欲しい」と言った。母は、
「それから?もっと買ってあげるから、言ってごらん」と言った。
私は、ハーモニカと木琴とカスタネットを買ってもらった。
それから母は、私を遊園地に連れて行った。入るのにも乗り物に乗るのもお金が要る遊園地に。こんな贅沢なことはしたことがなかった。が、母のどこかいつもと違う様子に、私はどうしたらいいのかわからず、ただ従った。
それでも遊園地は素晴らしかった、まるで別世界だ。電気が眩いばかりにきらめく夢のようなメリーゴーランドに、私は何回も何回も乗った。
「こればっかり、また?」と母が言ったが、私はその回転木馬の背中に乗ると、自分が何処かへ向かっているような、とてつもなく大きな何かを感じて、胸がワクワクするのだった。眩しいほど明るい電灯がいっぱい点いて、グルグルグルグル廻るのだ。
母は、ポツン、と立っていた。私を見ていた。
翌日、母は自分の洋服だけを持って、小さな三輪トラックの助手席に乗って行ってしまった。「明日、お父ちゃんが来るからね、」それだけ言って。
砂埃をたてて走り去る三輪トラックの後ろ姿が、次から次に溢れてくるいっぱいの涙でかすんでいった。その光景が、生涯、瞼に焼きついた。
部屋には、衣文賭けに掛けた母のスカートが一つ、ぶら下がっていた。
それは、母が、「これはおとうちゃんから買ってもらったものだから」と言って、置いていったものだった。
その晩、私は一晩中泣きじゃくっていた、木琴を叩きながら。
傍でおばあちゃんが途方にくれてオロオロしていた。私を慰めようとするのだが、おばあちゃんも泣いていた。
あの時の自分の悲しい想い、絶望的な悲しさは、いつまでたっても残った、痛く痛く。
今日もご縁を頂いてありがとうございました。
!VAYA CON DIOS!
あなたに幸あれ♪
自分語り 記事
下記リンクから「自分語り」をご覧ください。
◆序章 緑の島
◆幼年時代
◆第2章 自我の芽生え